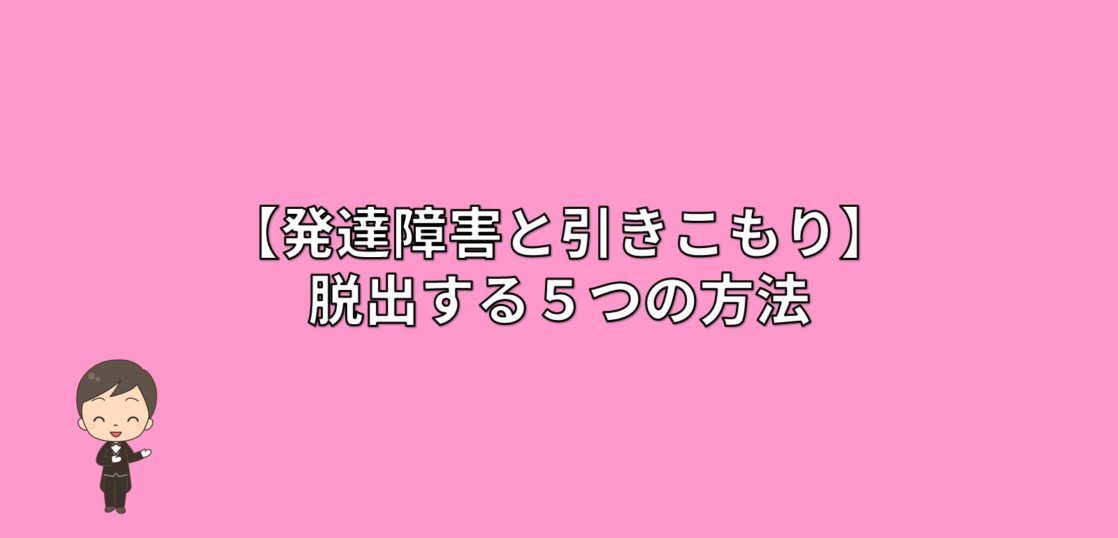学校に行かず、家族ともコミュニケーションをとらず、6か月以上続けて部屋にひきこもっている状態の「ひきこもり」。ひきこもりの約3割が「発達障害」と診断された報告があります。
もしお子さんが発達障害が原因で引きこもってしまった場合、引きこもりからどうやって脱出できるのでしょうか。
この記事では、原因から見る5つの方法をご紹介します。
引きこもりが悪化する状況とは?
引きこもりには、「個人(お子さん)」「家族」「社会」の3つが関わりあっています。
まず個人(お子さん)が誰とも関わらず、部屋にひきこもります。
家族は「なにかあったの?」と最初は心配しますよね。
けれど、いつまでもお子さんとコミュニケーションがとれない状態が続くと、焦りや不安を感じ、「いつまで引きこもってるの!」と悲しんだり、怒ったりしてしまいます。
するとお子さんは理解されないと感じ、ますます引きこもりに。
さらに引きこもりが悪化するのは、家族と社会が切り離されてしまうため。
引きこもりはネガティブなイメージが強く、ほかの家族や知人に話しにくいものです。
できれば他人に知られたくないでしょう。
そのため家族が誰にも相談せず、引きこもりの解決策がわからないまま時間が経ちます。
社会と家族が切り離された状態で、限界まで問題が放置されてしまいます。
このように個人・家族・社会それぞれにコミュニケーションがなく、切り離された状況が、最も子どもの引きこもりを悪化させます。
引きこもりからの脱出するには?
子どもが部屋に引きこもり、家族すら拒絶している場合、家族がどれだけ声をかけても解決しません。
引きこもりの原因が、子どもと家族とのコミュニケーションが問題になっている可能性があるからです。
この場合は、まず社会と家族がつながることが大事です。
①家族が支援機関に相談する
お住まいの市にある発達障害支援センターやひきこもり支援機関へ相談しましょう。
発達障害を診断する病院を紹介してもらえたり、お子さんとの接し方を教えてもらったりできます。
相談するのに抵抗があるかもしれませんが、引きこもりからの脱出には近道となります。
引きこもったまま、子どもが大人になり、事態が悪化するよりはマシです。
もし原因に心当たりがあるなら、早めに相談しましょう。
②カウンセラーなどが当事者と話し合う
引きこもりは周囲へ心を閉ざしている状態です。
病院の医師や支援機関に紹介されたカウンセラーなどが話をしていき、お子さんと信頼関係を築きます。
引きこもった理由を聞いたり、どのような特性があるかを明らかにしたりします。
③まわりが特性にあった支援をする
家族は明らかになった発達障害の特性を理解し、環境を変えないといけません。
感覚過敏があるようなら、音・光・ニオイなどに配慮する。こだわりが強い特性があるなら、無理にやめさせたりせず、別の方法を模索する。
予測できないことにたいしてお子さんが不安になる場合はスケジュール表を用意してあげて、先の見通しができるようにする。
家での不安・不満をへらし、コミュニケーションのとり方もお子さんに合わせて変えていくことで、家族と個人がつながれる状態になります。
④自助グループへの参加
お子さんとコミュニケーションがとれるようになっても、本人が学校に行くと言わないかぎり、「学校に行こう」と伝えるのはやめましょう。
引きこもっていた子がすぐに社会となじむのはむずかしいです。とくにいじめなど、まわり(社会)との関係に原因があった場合はもっと困難です。
いじめ問題を解決するように動いたり、発達障害の特性に合わせて特別支援級に行くなど場所を変えないといけないこともあるかもしれません。
まわりとの問題が解決したとしても、すぐに当時のクラスメイトに会うことはむずかしいでしょう。
体のリハビリと同じで、一度傷ついたものは少しずつ回復させていく必要があります。
まずは同じ悩みに苦しんだ人たちが集まる、自助グループに参加するほうがハードルが低いですね。
同じ仲間と悩みを共有することで、心が軽くなり、徐々に人やまわりに慣れていけるでしょう。
⑤薬物治療
発達障害の二次障害として、引きこもりのほかに不安障害やうつ病傾向などを発症していることがあります。
社会に慣れていったとしても、発作のようにパニックを起こす場合は医療と連携する必要がありますね。
小児科や精神科に相談し、医師の診断のもと、薬を処方してもらいましょう。
まとめ
引きこもりから脱出するには、「個人」「家族」「社会」が、つながりのある状態にしないといけません。
引きこもりが悪化するのは、3つがそれぞれ切り離されてしまった状態。
限界まで引きこもり問題を放置することがないように、3つのつながりを大切にしましょう。
まず子どもが家族とのコミュニケーションを拒否している場合は、家族が社会とつながることから始めます。
つぎに社会と家族が協力して個人に働きかけ、個人と家族、社会とつながりを広くしていきます。
一度引きこもってしまったお子さんと関わるときは、家族みんなが特性を理解し、当事者目線を忘れないように。
環境に配慮したり、コミュニケーションのとり方を合わせてあげてください。
そしてお子さんが家族、社会と慣れていけば、引きこもりから脱出できる日も近くなるでしょう。
引きこもりにならないために、早期からの社会性を育むトレーニングが必要とされます。
そうした早期のトレーニングは放課後等デイサービスなどでおこなわれています。
10人中9人が満足する療育プログラム
Polaris(ポラリス)教室では、お子さんの発達課題に合わせたプログラムをご用意します。
早期からの療育でお子さんの将来のできることを増やしませんか?
Polaris(ポラリス)教室でお子さんの課題に合った支援方法を一緒に探しましょう。